在宅でできる医療もありますが、施設では看護師や介護士などの資格保持者がいなければ喀痰吸引ができない場合もあります。
少し間違えると生命の危険があります。正しい、操作を覚えておくのは大事です。
- 在宅自己注射
- 悪性腫瘍疼痛管理
- 人工透析
- 在宅中心静脈栄養法/経管栄養法
- 在宅人工呼吸療法/酸素療法
- 喀痰吸引
- ストーマほか
在宅自己注射
利用者またはかご族が、自らあるいは利用者に対して注射をする。
- 糖尿病のインスリン注射
- アナフィラキシー時のエピネフリン注射
- 血友病の血液凝固因子製剤
- 肝炎のインターフェロン注射
インスリン自己注射は、体内のインスリン分泌の不足を補うために行う。
インスリンには血糖値を下げる働きがあり、過剰に投与したり食事を抜いたりすると低血糖をまねきます。
低血糖では、空腹感、冷や汗、動悸、意識レベルの悪化などが生じ、重症化すると意識障害や昏睡に至る。
- 食事摂取量に注意をはらい、発熱や食欲不振など体調不良時(シックデイ)で摂取量が少ない時の対処法(インスリンの用量を減らす、打たないなど)を確認しておく
- 低血糖の症状がみられたら糖分を補給する。経口摂取が難しい場合は、すぐに医療職に連絡する
- 注射するインスリン製剤の種類、1日の回数、1回の量について、医師の指示を確認しておく
悪性腫瘍疼痛管理
末期がんによる身体的な痛みを緩和するものです。
痛みの緩和には、おもに麻薬が使われますが副作用として吐き気、嘔吐、眠気、便秘などが生じる。
- 飲み薬を使うことが基本ですが、がんの進行により経口摂取が難しくなると張り薬や座薬、注射薬などが用いられます。
- きめ細やかな薬剤量の管理が必要な場合は、自動注入ポンプを使用した注射薬の持続的投与が行われることがあります。
- 副作用への対応方法、自動注入ポンプのトラブル発生時の対応方法を、利用者、介護者、支援者の間で共有しておく必要がある
人工透析
腎機能の低下により、血液のろ過が十分に行えず老廃物や水分の調節ができなくなった場合、人工透析の適用となります。
- 血液を体外に取り出し、ろ過して戻す
- 専門施設(病院など)で行われる
- 週に2~3回の通院
留意点
- 水分、塩分、リン、カリウムの摂り過ぎに注意
- 透析用血管(シャンと)への圧迫を避ける
- 腹腔にカテーテルを留置し、透析用液体を注入して腹膜の作用で血液をろ過し、老廃物を含む廃液を排出する
- 自宅でできる
- 月に1~2回の通院
- 食事制限が緩い
留意点
- 長期間にわたって腹膜透析を続けた場合、腹膜が変化して透析ができなくなる
- カテーテルから細菌が感染するリスクがある
- 利用者や介護者が病気に関する知識や清潔な手技について十分指導を受けている必要がある
人工透析を受けている利用者は、体調が悪くなる
心筋梗塞や脳血管障害等の疾病リスクが高くなるなどの傾向があり、注意が必要です。
血液透析の場合は、水分、塩分、リン、カリウムの摂り過ぎに注意し、透析用血管(シャント)への圧迫を避けます。
在宅中心静脈栄養法
十分な食事がとれず、必要な栄養を摂取できなくなった場合、高濃度栄養剤を点滴により直接血管に注入し、栄養を補給する方法が中心静脈栄養法です。
- 長期間続けると消化吸収機能が低下するおそれがある
- 使われれの葉心臓の近くにある太い静脈(中心静脈)
- 鎖骨下などから中心静脈にカテーテルの先端を入れて固定する
- カテーテルの橋をそのまま外に出す方法と皮下に埋め込む方法(ポート型)があります。
- 入浴は可能だが、特別な配慮が必要になるので、医療職と相談する
- 感染防止、カテーテル抜去事故の防止に注意が必要
- 輪液用バッグ、接続チューブなどの扱いに注意する
- 点滴が落ちない、カテーテルが抜けた、出血したなど、トラブル発生時の対応をスタッフ内で周知しておく
経管栄養法
十分な食事がとれず櫃よ言うな栄養を摂取できなくなった場合、胃や腸に直接栄養剤を注入する方法が経管栄養法です。
胃や腸で栄養を消化吸収するという本来の機能を活用するため、中心静脈栄養法に優先して選択される
| 種類 | 概要 |
| 経鼻胃管 | 鼻からカテーテルを入れて胃に留意する |
| 食道ろう | 首の皮膚から食道に達する穴をあけてカテーテルを入れて胃に留置する |
| 胃ろう | 皮膚の表面から胃に達する穴(ろう孔)を開けて、栄養剤を注入する |
| 腸ろう | 胃ろうが難しい場合に、皮膚の表面から腸に達するろう孔を開けて、栄養剤を注入する |
胃ろうの種類
胃ろうによる経管栄養法では、ろう孔に設置されたカテーテルを固定するために、体外固定板と胃内固定板を使用します。
- 体外固定板はボタンとチューブ
- 胃ない固定板はバルーンとバンパー
- 体外固定板のうち、抜けにくいのは、外に出ている部分の少ないボタン型
- いない固定板のうち、バルーン型は交感しやすい一方で、破裂により短期間で交換する必要があるのが特徴
- カテーテル周囲の皮膚(鼻腔、ろう孔周囲)の観察と清潔ケアに配慮する
- 経鼻胃管では、カテーテル固定位置を変えて潰瘍ができるのを防止する
- 栄養剤を注入する時は、利用者の上半身を30度以上起こし、逆流や誤嚥を予防する
- 栄養剤の種類、注入速度、注入量は医師の指示内容を守る。注入速度が速すぎると下痢を起こしたり、嘔吐したりすることがある
- 経鼻経管では、利用者がカテーテルを抜くことがあるので注意する
- 胃ろう・腸ろうでは、カテーテルが内部に入り込んでしまうバンパー埋没症候群を予防するため、定期的にカテーテルが回転するか確認する
- 胃ろう・腸ろうでは、カテーテルが抜けるとろう孔がふさがってしまうので、速やかに医療職に連絡する体制をつくる
在宅呼吸療法
呼吸機能が低下し十分に酸素の取り込みと二酸化炭素の排出が出来なくなった場合、人工呼吸器により呼吸を補助するのが人工呼吸療法です。
侵襲的陽圧換気法(IPPV) ⇒ 気管切開して気管カニューレを挿入する
非侵襲的陽圧換気法(NPPV) ⇒ マスクなどを使用する
心臓や血管、気管、鼻などに挿入・装着するチューブのこと
- トラブルが生命の危険に直結する
- 急変時や機器トラブルの予防と対応について医療職から十分な情報をもらい、連絡体制を整えておく必要がある
- 非常時に備え予備の電源供給装置やアンビューバッグ(手動式の人工呼吸器)を用意し、使い方を習熟しておくことも必要
- 日常的には、気管切開部周辺の皮膚の観察と清潔ケアに留意
在宅酸素療法
呼吸器疾患や心疾患などにより低酸素血症をきたしている場合に、鼻カニューレや酸素マスクなどを用いて酸素を吸入して症状を抑え、ADLや生命予後の改善を図る方法です
鼻カニューレにようる在宅酸素療法は、両側の鼻腔にカニューレを装着して酸素を吸入する方法です。
酸素マスクによるものと異なり、口の部分が空いているので食事や会話がしやすいのが特徴
機器の小型化・軽量化により入院が必要だった人の多くが在宅で生活できるようになっています。携帯型酸素ボンベを使えば外出も可能です。
- 高濃度酸素を扱うため、機器は火気から2m以上離す
- 喫煙、コンロの使用など直接火を扱う機会はできるだけ避ける(禁煙する、電磁調理器やエアコンに替えるなど)
- 吸入用器具の洗浄・消毒、点検をこまめに行う
- 酸素の流量は医師の指示範囲で行う
- 酸素飽和度、脈拍、血圧、呼吸状態などを把握し、体調の変化に注意する
- 入浴は、酸素の必要量を増加させるため、カニューレをつけたまま入浴する
動脈血酸素飽和度。血液中にどの程度の酸素が含まれているかの値。健康な人の基準値は95~100%。パルスオキシメーターを指にはさむことで簡便に測定できる。
高濃度の酸素を吸うことで、呼吸がかえって抑えられ、意識障害をおこす。酸素療法時に酸素の流量をむやみに上げると、CO₂ナルコーシスを生じる危険があるので注意が必要です。
喀痰吸引
喀痰吸引は、自力で痰を吐き出すことができない場合や気管切開をしている場合などに、口腔や鼻腔、気管カニューレなどからチューブを入れて、痰を吸引する処置です。
喀痰吸引は、介護職が行える医療的ケアの範囲に含まれており、窒息や肺炎などを予防するために行うもので、気管切開、人工呼吸器装着では欠かせません。
- 吸引時は感染防止に留意し、吸引用チューブは毎回洗浄・消毒します
- 最近は使い捨てチューブが使用されるとこが多い
- 気管カニューレ内部の吸引では、無菌操作が必要です
- 吸引器は医療機器に該当し、介護保険の給付対象になりません。難病等の場合は補助が受けられることがある
- 介護職が行うことのできる喀痰吸引の範囲は、口腔内鼻腔無いの喀痰吸引では咽頭の手前まで、気管カニューレを挿入している場合は気管カニューレ内部までです
ストーマ、バルーンカテーテル、在宅自己導尿
通常の排泄が難しい場合に選択される
ストーマ(人工肛門・人口膀胱)
- ストーマとは、人工的な排泄口をいい、消化管や尿路障害で通常の排泄ができない時に排泄ルートとしてつくられる
- 腸や尿路に開口部を設け採尿や齋弁用のパック(パウチ)を装着するもので、消化管ストーマ(人工肛門)と尿路ストーマ(人口膀胱)に分けられる
- 食事や入浴、外出などは特に制限はありません
- オストメイトマークはオストメイトのための設備があることを表しています
バルーンカテーテル(膀胱留置カテーテル)
- 尿道から膀胱へカテーテルを挿入して留置し、持続的に尿を排出する
- 膀胱に入っているかテール先端を風船上にふくらませて抜け落ちないようにする
- 尿は畜尿バッグを装着してためる
- 完全に尿が出ない(尿閉)場合や不完全な排尿しかできない場合などに使用する
- 膀胱より高い位置に畜尿バッグがあると尿の逆流が起こり感染の危険があるため、移動時などには注意する
- 長く留置し続けると尿路感染んおリスクが高くなる
在宅自己導尿
- 在宅自己導尿とは自分で尿管にカテーテルを挿入し、尿を排泄する方法です
- 神経障害などにより自然排泄が困難な場合などに使われます
- バルーンカテーテルに比べて感染のリスクが低く、畜尿バッグも不要
- 手技に慣れることと、導尿時の感染防止に留意する必要がある
- 外出時などでは導尿が行える場所の確認が必要
まとめ
- 在宅医療管理の在宅は自宅、特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなど病院や老人保健福祉施設以外のことを指しています
- 看護師が不在でも、自宅、特別養護老人ホーム、グループホーム、有料老人ホームなどで働く介護職は在宅医療管理に対応しなければならない
- 病院や老人保健施設では、看護師が常駐していることが多く医療管理される
- 喀痰吸引は、看護師か研修を受けた介護職でなければできませんので24時間対応することは難しい
- 在宅医療管理は、自分で行うことができますが、重介護度の方はそれができません。だから、介護職のケアが必要です
- 介護職は在宅医療管理の方法を知らなければいけません
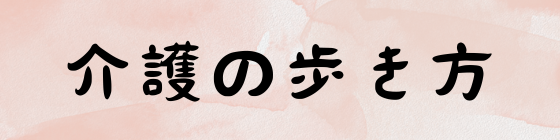
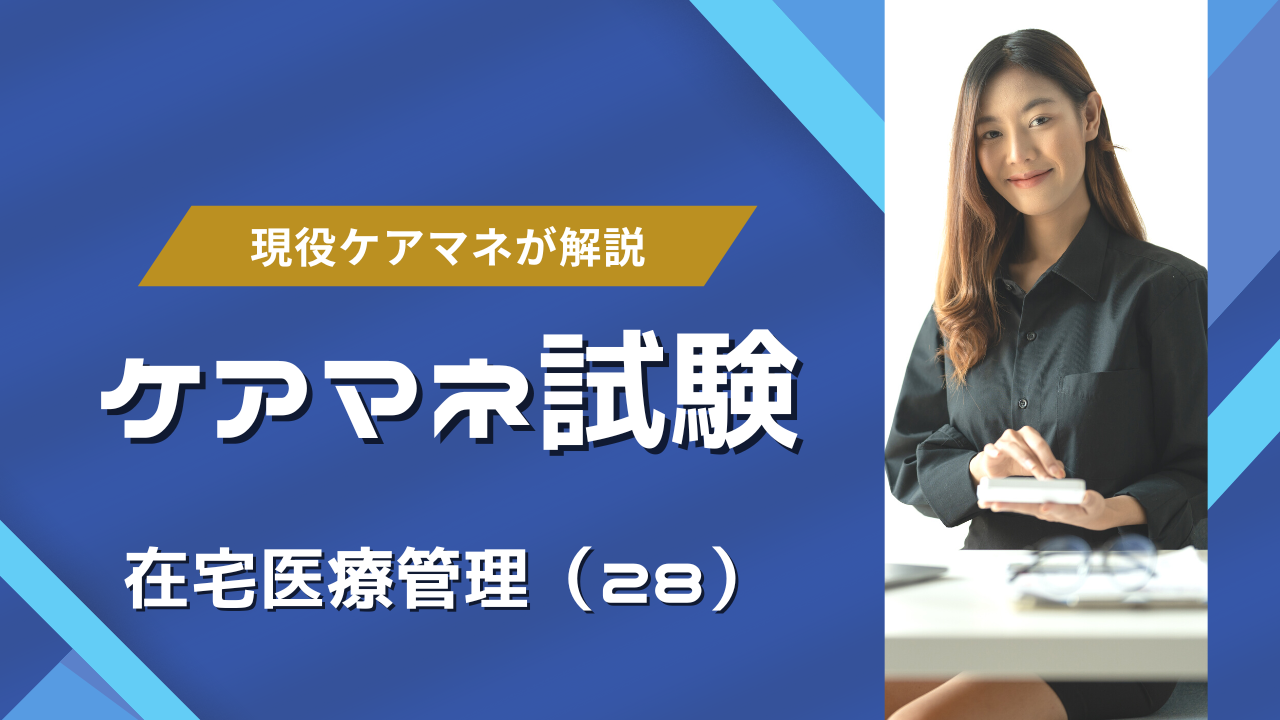

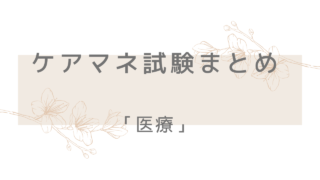
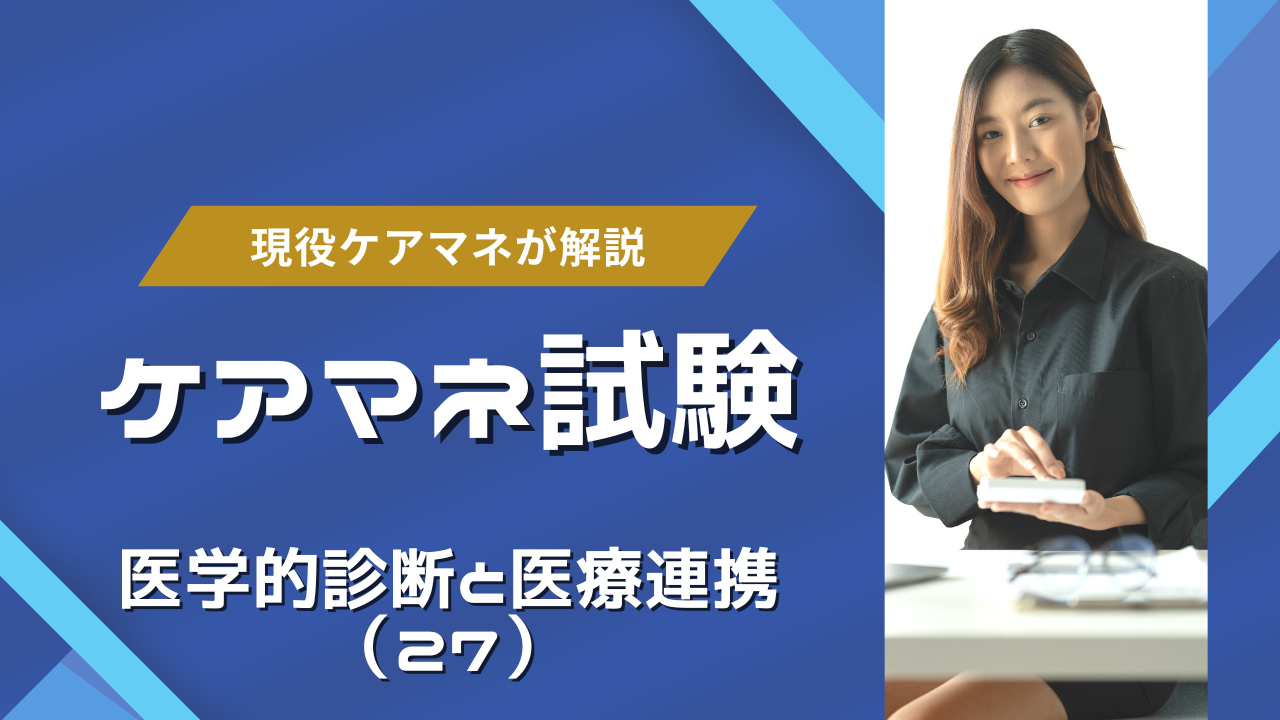
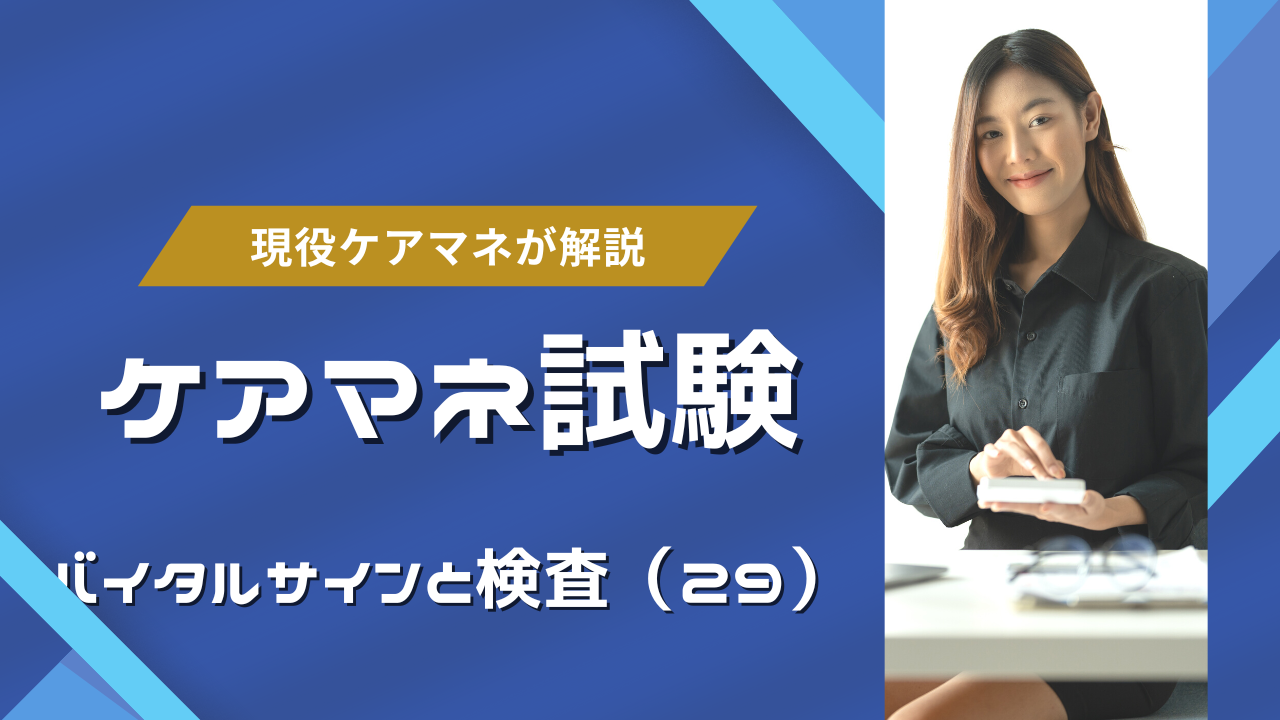
コメント