地域包括ケアシステムの核となるのが地域包括支援センターです。
要支援者のケアプラン作成だけでなく高齢者の悩みを解決する業務を行っています。
地域包括支援センターの業務を正確に理解することが重要です。
要支援の利用者様が多い事業者ではお世話になるのが地域包括支援センターです。
- 地域包括ケアシステムとは
- 地域包括支援センターの位置づけ
- 地域包括支援センターの業務とは
- 地域ケア会議とは
地域包括ケアシステム
簡単にいえば、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けることができるシステムでその中心に地域包括支援センターがあります。
十分かつ適切な医療、介護、介護予防、住居、生活支援などのサービスを切れ目なく提供することで、その人らしい自立した日常生活を地域で送ることを可能にする。

地域包括支援センターの位置づけ
地域包括支援センターを設置できるのは
- 市町村
- 市町村から包括的支援事業の委託を受けた法人(以下の法人)
- 老人介護支援センターの設置者(委託)
- 一部事務組合または広域連合(委託)
- 医療法人(委託)
- 社会福祉法人(委託)
- 公益法人(委託)
- NPO法人(委託)
センターの設置・運営に関しての責任主体は、市町村
市町村が事務局となって設置する地域包括支援センター運営協議会の議を経る。
地域包括支援センター運営協議会
- 原則、市町村単位で設置される
- 事業者・関係団体・被保険者等で構成
- 中立性・公平性の確保、人材確保支援など
職員配置基準
- 担当区域あたり第1号被保険者数3000人以上6000人未満につき、以下の常勤専従職員を各1名配置
- 保健師またはこれに準ずる者
- 社会福祉士またはこれに準ずる者
- 主任ケアマネージャーまたはこれに準ずる者
2017(平成29)年の介護保険法改正により、地域包括支援センターの設置者には、実施する事業の質の評価を行い事業の質の向上を図ること
市町村には、定期的に、地域包括支援センターにおける事業の実施状況について評価を行うことが義務化された。評価基準は、国が示す。
地域包括支援センターの業務
- 包括的支援事業
- 市町村の委託を受けて介護予防・日常生活支援総合事業や任意事業
- 指定介護予防支援業者になると介護予防支援
- 2014(平成26)年の介護保険法改正により、地域包括支援センターの機能強化が図られる
地域包括支援センターの機能強化
- 高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化
- 市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す
- 直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置付けるなど、センター間の役割分担・連携を強化
- 地域包括支援センター運営協議会により評価等により、継続的な評価・点検を強化
- 地域包括支援センターの取り組み関する情報公表を行う
地域ケア会議
地域ケア会議の開催は2014年(平成26)年の介護保険法改正までは地域包括支援センターが開催していました。
現在は、市町村による会議の設置が規定されました(努力義務)
2017(平成29年)の改正により、会議は厚生労働省の省令に従うことが義務づけられました。
地域ケア会議の機能
- 個別問題の解決 ⇒ 支援困難事例などの個別課題を取り上げ、多職種の協働による支援を通じて解決につなげる
- 地域包括支援ネットワークの構築 ⇒ 会議を通じて支援が必要な人を支えるための関係者によるネットワークを構築する
- 地域課題の発見 ⇒ 個別課題の解決事例を蓄積することにより、地域課題の発見につなげる
- 地域づくり・資源開発 ⇒ 住民との役割分担を図りながら地域に必要な資源を創出する
- 制作の形成 ⇒ 地域課題に対応する有効なサービスの基盤整備などを事業化、施策化するなど、政策の形成につなげる
まとめ
- 施設に入らず自宅で生活するために地域の状況を把握する
- 地域の状況を把握したら問題解決をする
- 介護給付が必要な方は、要支援限定でケアプランを作成したり制度のご案内や相談を受け付ける
- 地域を支えるボランティアやNPOの支援を行う
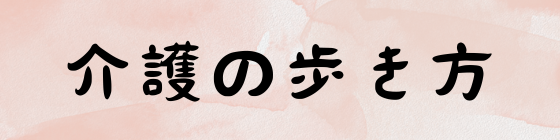
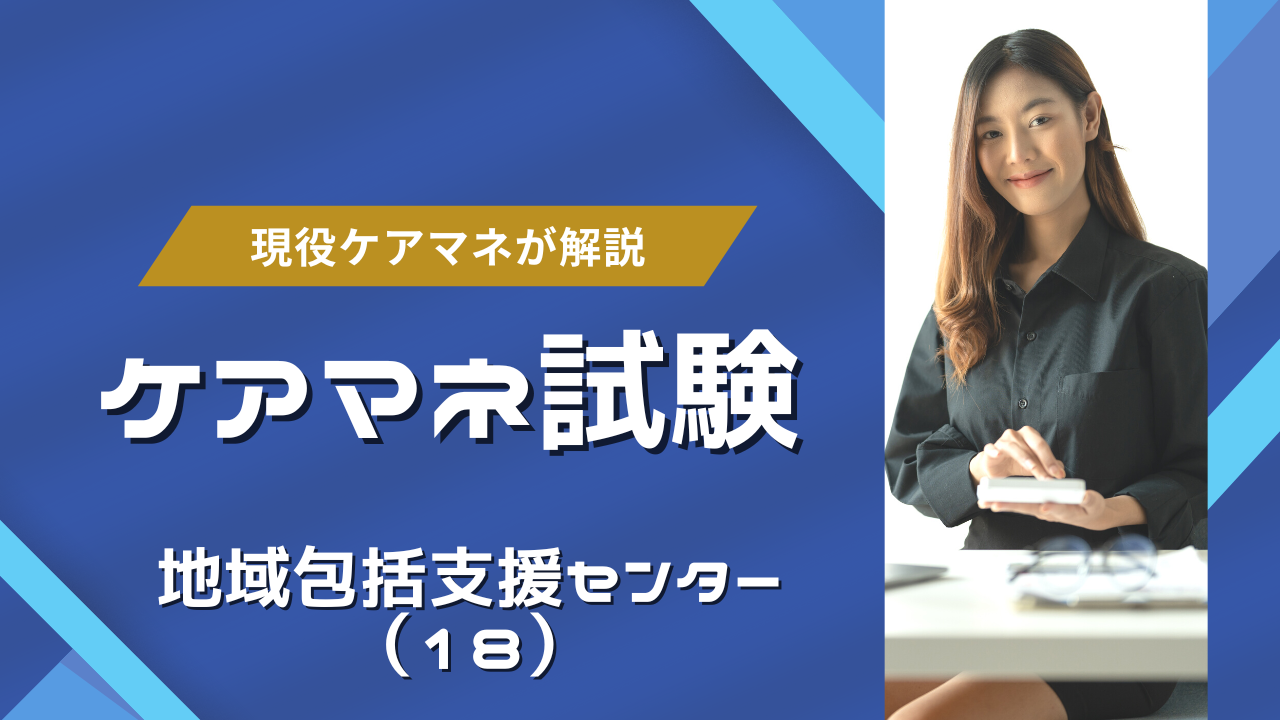

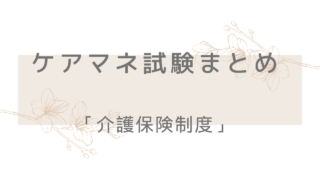
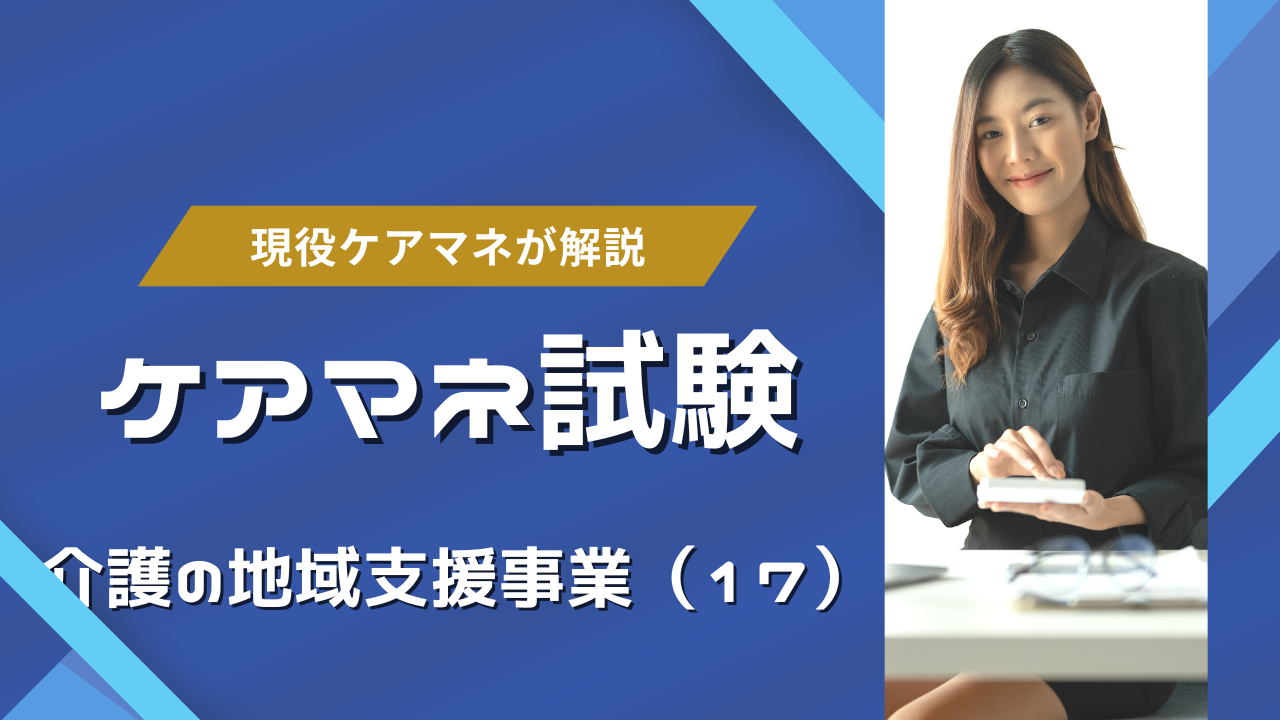
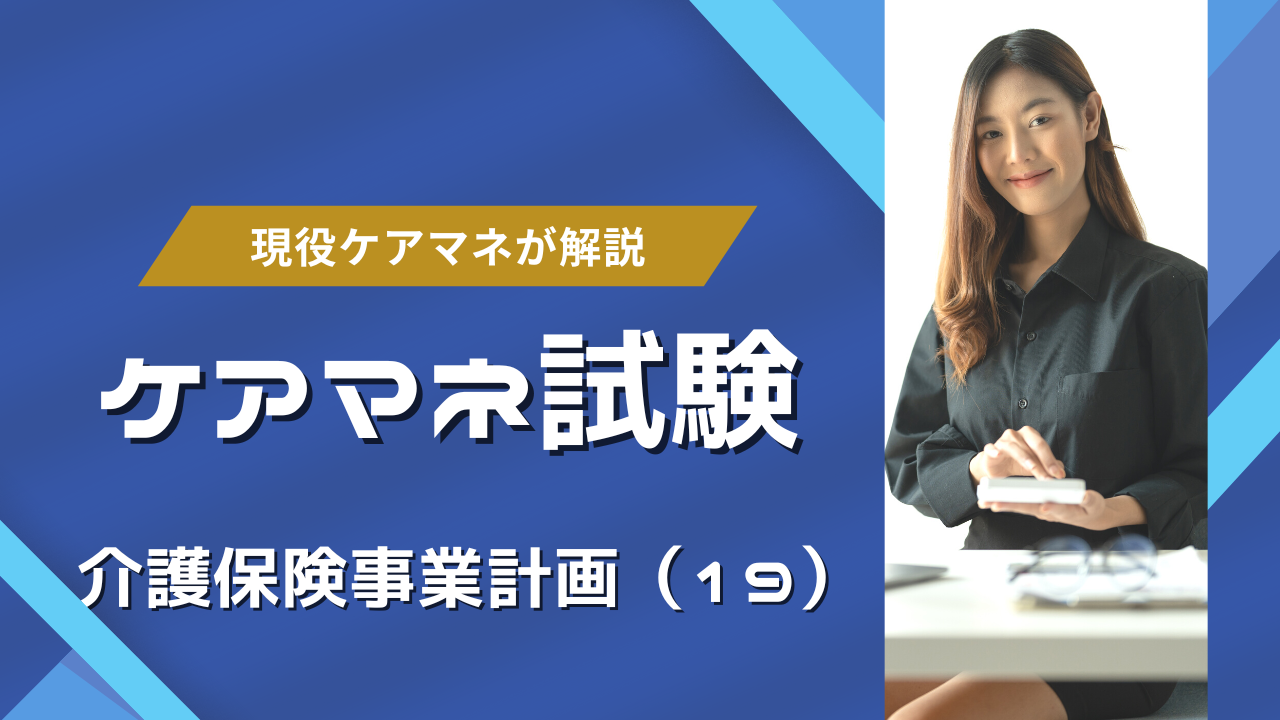
コメント