日勤帯、夜勤帯ともに急変時の対応はあります。
日勤帯はスタッフや看護師が出勤していることが多いので対応もスムーズなのですが夜勤帯となると自分の判断で救急搬送、様子観察、クーリング、主治医への連絡をしないといけません。
判断基準がわかっていれば急変の対応も難しくはないのですが、知らないと緊張で自分が大変なことになります。
- 事故が起こり急変となる
- 病的な症状がある
高齢者に起こりやすい急変
- 高齢者の疾患の特徴として、慢性疾患、複数疾患、症状が非定型的、自覚症状や訴えが少ない
- 自覚症状が少ないことから疾患が重症化しやすい
- 突然の精神症状や意識障害
- 水や電解質の代謝異常(脱水)
- 薬の副作用がでやすい
- 高齢者は歩行の不安定さやバランス力の低下で転倒しやすく、転倒すると骨折しやすい
- 窒息や入浴中の溺水などの不慮の事故が多い
- 急変時の対応は、医療と介護の連携が重要
- あらかじめ予想される急変への対応方法、受診先、連絡方法などを決めておく
- 急変時の初期対応がそのまま予後に直結する
事故への対応
転倒
高齢者は、運動期間が不安定になるのに加え、平衡機能や視力の衰え、認知機能の低下などにより、転倒の危険が増します。
転倒を発見したら、転倒の状況や身体状況の把握に努め、各病態に対しては次のように対応しますが、いずれの場合も速やかに医療機関に連絡します。
| 病態 | 対応 |
| 出血 | ・大きな傷がある場合は、傷口を清潔なガーゼやタオルで圧迫して止血 ・激しい出血や、清潔なタオル等がない場合は、出血部位よりも心臓に近い側を圧迫し、出血部位を芯ゾノ位置より高くする |
| 打撲 | ・頭部打撲で、記憶障害や頭痛、嘔吐などがみられる場合は、当該内の出血が疑われるので検査が必要 ・頭部打撲で、両手足の脱力や痺れなどがみられる場合は、頸椎損傷が疑われ、動かすと悪化するので極力動かさないようにする ・腹部の打撲で、下腹部が膨らんでくる場合は、肝臓や脾臓からの出血が疑われる |
| 骨折 | ・転倒により骨折しやすい部位は、大腿骨頸部、手首、上腕骨頸部で骨折が疑われたら動かないように固定する 骨が皮膚から出ている開放性骨折では、感染のおそれがあるので触れないようにする |
誤嚥(窒息)
- 高齢者は、嚥下機能の低下による嚥下障害が生じやすく、誤嚥や窒息が起こりやすくなります
- 誤嚥により、呼吸困難が生じると自分の喉を親指と人差し指でつかむチョークサインや、手足をばたつかせるなどの窒息サインやチアノーゼなどがみられます
- 高齢者は窒息した場合に苦しがらずにじっとしていることもあるため注意が必要
- 異物を誤嚥した場合、咳を出させることで排出できることがある
- 詰まった異物がより奥に行かないように側臥位にさせ、口の中の異物を確認し指でかきだす
- どうしても異物が出ない場合は、背中をたたく背部叩打法、背部から手を回しみぞおちを突き上げる腹部突き上げ法(ハイムリック法)などで異物を除き、同時に医療機関に連絡します
- 腹部突き上げ法は、臓器を傷つけることがあるので行った場合はその旨を伝える
誤薬
誤薬とは、誤った種類、量、時間または、方法で薬を服用することをいいます。
- 服用してしまった薬の種類や量によっては、生命に関わるので誤薬に気付いたら胃の内容物を吐かせます
- 血糖降下剤の多用やインスリン自己注射の量の誤用では低血糖を引き起こす危険があるので、ブドウ糖や砂糖、ジュースを飲むなどして対応します
- 誤薬に気付いた時に意識がない場合は、呼吸しやすい体位にして救急車の手配をします
熱傷(やけど)
- やけどの範囲が狭い場合は、水道水などの冷水で15~30分間、痛みがなくなるまで冷やす
- 衣服の下をやけどした場合は、衣服を脱がすと痛みが増強したり、出血を起こしたりするので、衣服の上から冷やす
- やけどの範囲が広い場合は、速やかに救急車を要請するとともに、シャワーの水で冷やしますが、低体温や血圧の低下などで意識障害を引き起こすこともあるので注意が必要
溺水
- 溺水のほとんどは、入浴中に浴槽内で発生
- 血圧変動が大きくなるため、心筋梗塞や脳血管障害をきたして意識障害を起こして溺れてしまう
- 異常を発見した場合は、ただちに浴槽から出し、心肺蘇生を行う
心停止
- 心停止の場合は、ただちに心肺蘇生が必要、同時に救急車を要請
- 心停止が3分以上続くと重大な脳障害が生じる
- 心肺蘇生法は胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸は誰でも出来る一次救命処置
- AEDをした後に心肺蘇生
心臓に電気ショックをすることで、心臓を正しいリズムに戻すこと医療機器。
音声ガイドに従って操作するもので2004年7月より、一般の人も使用することができるようになった。右のハートに稲妻のマークは、AED設置場所を意味するマーク。

呼吸をしやすくするために、酸素の通り道を確保すること。代表的な手法は頭部後屈顎先挙上法(片手は額に、もう一方の手は人差し指と中指を顎先に当てて、頭をロ代にのけぞらせて顎先を上げる方法)。
身体変化への対応
意識レベルの低下、ADLの低下
基礎疾患によるもの以外に脱水や熱中症、脳虚血などでも起こります。
急変に伴うことも多く、意識レベルの程度を把握し、医療関係者に伝えることが疾患の重症度などの判別に重要です。
なお、意識レベルの程度の評価にはジャパン・コーマ・スケール(JCS)が良く使われます。在宅の利用者に意識障害がある場合は、救急車を要請します。
腹痛・嘔吐
腹痛の原因はさまざまで、多くの疾患で起こります。
腹痛では、悪化の恐れがあるので患部を温めたり冷やしたりせず速やかに医療機関に連絡します。また、安易に鎮痛薬を使わないようにします。
嘔吐がみられたらのどが詰まらないように横向きに寝かせ、口に残った異物を取り出します。
意識や呼吸状態が悪い場合や吐いたものに血が混じっている場合は、速やかに医療機関に連絡します。
激しい腹痛と嘔吐を繰り返す場合は、イレウス(腸閉塞)、腹痛・嘔吐に加えて、発熱がみられる場合は、食中毒やノロウイルス感染などが疑われます。
吐血、下血、喀血
消化管出血を起こし、
口から血を吐くことを吐血
肛門から出血することを下血
胃・十二指腸潰瘍、胃がんなど上部消化管の疾患で便に混じって黒色のタール便を生じる。
肛門に近い下部消化管からの出血で鮮紅色の下血を生じる。
喀血は、喉頭や気管・気管支、肺胞などの気道系からの出血が気道を通って口から吐き出すことをいいます。速やかに医療機関に連絡します。
- 腹部が緊張しないように膝を曲げて立て
- 静かに寝かせて
- 身体と頭を横向きにする
- バイタルサインを確認し
- 膝を曲げて静かに寝かせて
- 嘔吐がある時は顔を横向きにし
- 悪寒がある時は保温する
- 検束への血液流入、窒息等の防止のため出血側を下にした側臥位にし
- 口腔内の血液をぬぐい取り
- 胸側を上にして頭部を下げる(体位ドレナージ)
出血や嘔吐の誘引、腹痛の増悪などを引き起こす恐れがあるので、水や薬などは飲ませないようにします。
呼吸不全(呼吸変化)
呼吸困難や息切れは多くの疾患でみられる症状です。
呼吸困難が突然起こった場合、様子がいつもと違う場合は、緊急性が高くなります。
人工呼吸や気道確保が必要になることがあります。緊急性が高くない場合は、座位など呼吸が楽な姿勢をとらせます。
まとめ
- 事故の内容によっては、重篤な結果になります
- 転倒は、ADLが低下した方に多くみられます
- 誤嚥によって、肺炎や窒息などが起こります
- 誤嚥は、嚥下機能が低下した方がなりやすいのでリハビリによって嚥下機能の低下を防止しなければいけません
- 誤薬は、他者と薬を間違える人為的なミスで起きます
- 火傷は、熱いお茶をこぼしたりすることで起きることがありお茶の提供は温度が冷めてからの方がいいです
- 溺水は、入浴中に起きやすいので目を離すことはできません
- 心停止では、AEDの操作が慣れていなければいけません
- 身体変化は、病的な症状のサインになります
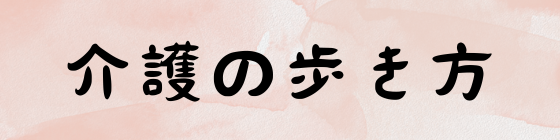
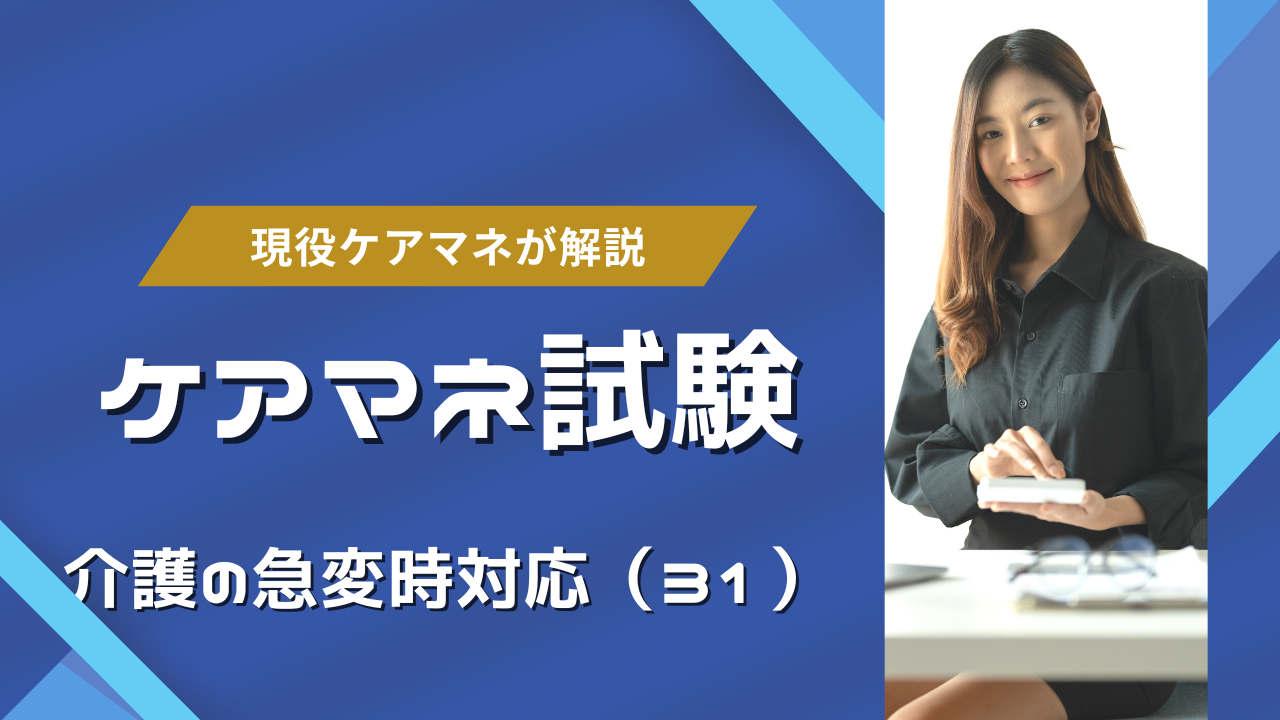

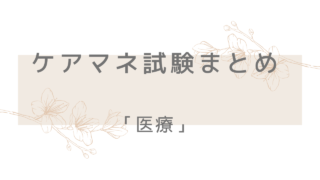
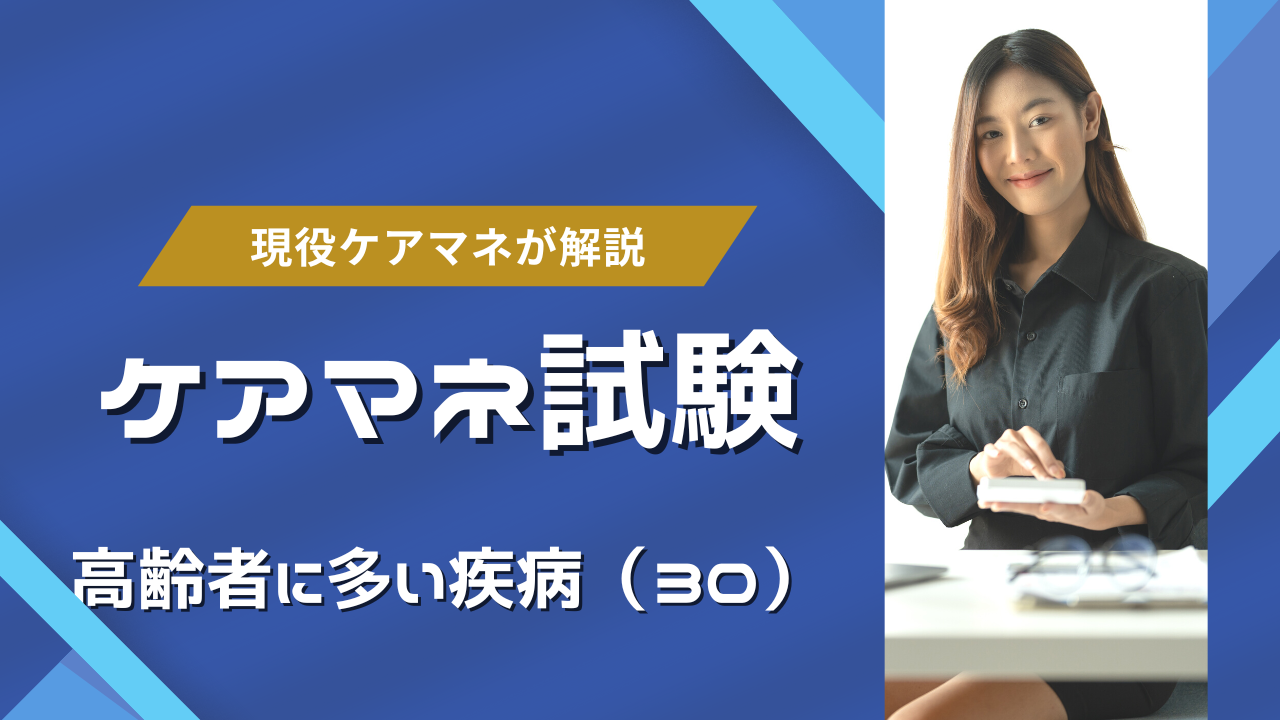

コメント