保険給付の財源は保険料のみで足りているのか?
足りなければどうやって補っているのか?
国、都道府県、市町村の財政負担はどのような割合なのかを解説していきます。
- 介護給付費は負担割合がある
- 公費は国、都道府県、市町村で負担割合がある
- 第1号保険料の用途
- 第2号保険料の用途
- 保険料率の設定方法
- 保険料の徴収 普通徴収と特別徴収
- 保険料の滞納 1年以上の滞納 1年6か月以上の滞納 2年の時効で消滅
- 保険料減免の3原則
- 社会保険診療報酬支払基金
- 第2号保険料の保険料 健康保険 国民健康保険
- 財政安定化基金
- 市町村相互財政安定化事業
財政構造
介護給付費 公費50% 保険料50%

公費
- 定率の国庫負担金
- 調整交付金 → 各市町村の後期高齢者の割合、第1号被保険者所得格差、災害時の保険料減免などを考慮して市町村ごとに調整されて交付
- 定率の負担
- 定率の負担
- 介護保険に関する事務に要する費用を全額負担
保険料
保険料は、平均保険料を同水準にするため被保険者の人口比率を考慮して3年ごとに見直される
- 介護給付費
- 地域支援事業・保健福祉事業
- 市町村特別給付
- 財政安定化基金拠出額
- 保険料率は、各市町村が条例で定め、3年ごとに見直す
- 所得段階別定額保険料 → 原則9段階で条例によって段階を細分化したり保険料率を品行出来る。
- 所得段階は、市町村民税の課税・非課税、本人の収入で決まる
- 介護給付費
- 地域支援事業のうちの介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険事業に関する支出額 - 公費等による収入額 = 差額
差額を第1号保険料でまかなう額
支出額 → 保険給付額、財政安定化基金への拠出金額、償還金、地域支援事業・保健福祉事業の費用、市町村特別給付の給付額、事務費等
収入額 → 公費(国、都道府県、市町村の負担分)、介護給付費交付金等
保険料の徴収
| 分類 | 徴収方法 | 対象者 | 備考 |
| 特別徴収 | 年金から天引きする | 年額18万円以上の公的年金収入が ある被保険者 | 市町村から介護保険料額の通知を 受けた年金保険者が、保険料を年金 から徴収し、市町村へ納入する。 |
| 普通徴収 | 納付書を送付し、徴収する | 年金等の収入が年額18万円に満た ない被保険者 | 本人納付が原則で、配偶者あるいは 世帯主に連帯納付義務がある。 収納事務は委託でき、コンビニエン スストア等でも支払いが可能 |
生活保護の被保護者は福祉事務所が介護保険料を被保護者に代わって市町村に直接支払うことができる
保険料の滞納
1年以上の滞納 → 現物給付化がなくなり、償還払いになる 介護給付の支払い方法の変更
1年6か月以上の滞納 → 保険給付の一時差し止め 保険給付の相殺
要介護認定等以前の滞納保険料が時効2年で消滅 → 保険給付を受けるようになった時、消滅した機関におうじて、保険給付割合が減額される。また、高額カイゴサービス費等の利用者負担を軽減する給付が不支給される。
滞納は災害等の特別な事情がある場合は、これらの措置の対象になりません。
保険料の減免
災害などの特別の理由がある場合、市町村は条例を定めて、保険料の減免や徴収猶予をすることができます。
- 保険料の全額免除
- 収入のみに着目した一律減免
- 保険料減免分に対する一般財源の投入
すべて禁止
第2号保険料
保険料の徴収と交付

医療保険の診療報酬の審査・支払いを行う機関。
介護保険関連業務として、医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金の徴収、
市町村に対する介護給付費交付金の交付、市町村に対する地域支援事業支援交付金の交付
これらに附帯する業務を行う。
保険料の額
保険料は各医療保険者が保険料率を決めて計算します。
- 標準報酬月額に保険料率をかけて計算
- 被保険者と事業主が折半で負担
- 被扶養者に40歳以上65歳未満の特定被保険者の介護保険料を徴収する制度がある
- 2017年7月までは、被保険者に応じて納付金を負担する人頭割(加入者割)
- 2017年8月からは、報酬額に比例して負担する総報酬割が段階的に導入
- 2020年度からは、総報酬割を完全に実施
納付額 - 国庫負担金 を被保険者の所得や人数で調整し、所得割額、被保険者均等割額などを計算する。
世帯単位の納付額総額を世帯主から徴収
財政安定化基金
市町村の介護保険財政の安定化を図るため、都道府県に設置
- 保険料未納による収入不足に対する交付金の交付(2分の1を交付、2分の1を貸付)
- 給付費の増大に対する不足額に対する資金の貸付
- 貸付を受けた市町村は、次の介護保険事業計画期間に、第1号保険料を財源として3年間の分割、償還期限は無利子で返済
- 基金の財源は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担
市町村相互財政安定化事業
複数の市町村が共同して、各市町村の保険給付額の合計と収入額の合計が均衡するように「調整保険料率」を定めて、全体で財政の安定化を図る事業
ある市町村の不足分を他の市町村の収入でまかなうという調整をする。
市町村相互財政安定化事業を行う市町村を特定市町村という。
都道府県は、特定市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整や、調整保健率の基準の提示などの必要な
まとめ
- 介護保険の財源は、被保険者が50%、国などが合計50%負担してます
- 少子高齢化になり介護保険給付が増大していくと被保険者と国などの財源負担んも増大していきます
- 介護保険料が増加し、税金も増加していきます
- 介護保険料を滞納している方がいると財源が不足してきます
- 財政安定化基金や市町村相互財政安定化事業という制度を設けて安定的な介護保険給付を実現しようとしています
- 財政は介護保険事業計画で作成されます
- 3年ごとの保険料の設定を行っています
- 第1号保険料と第2号保険料の使途に違いがあり、単純な暗記です
- 暗記のしにくい分野ですが、イメージを持って学習していきましょう
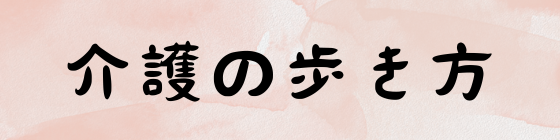
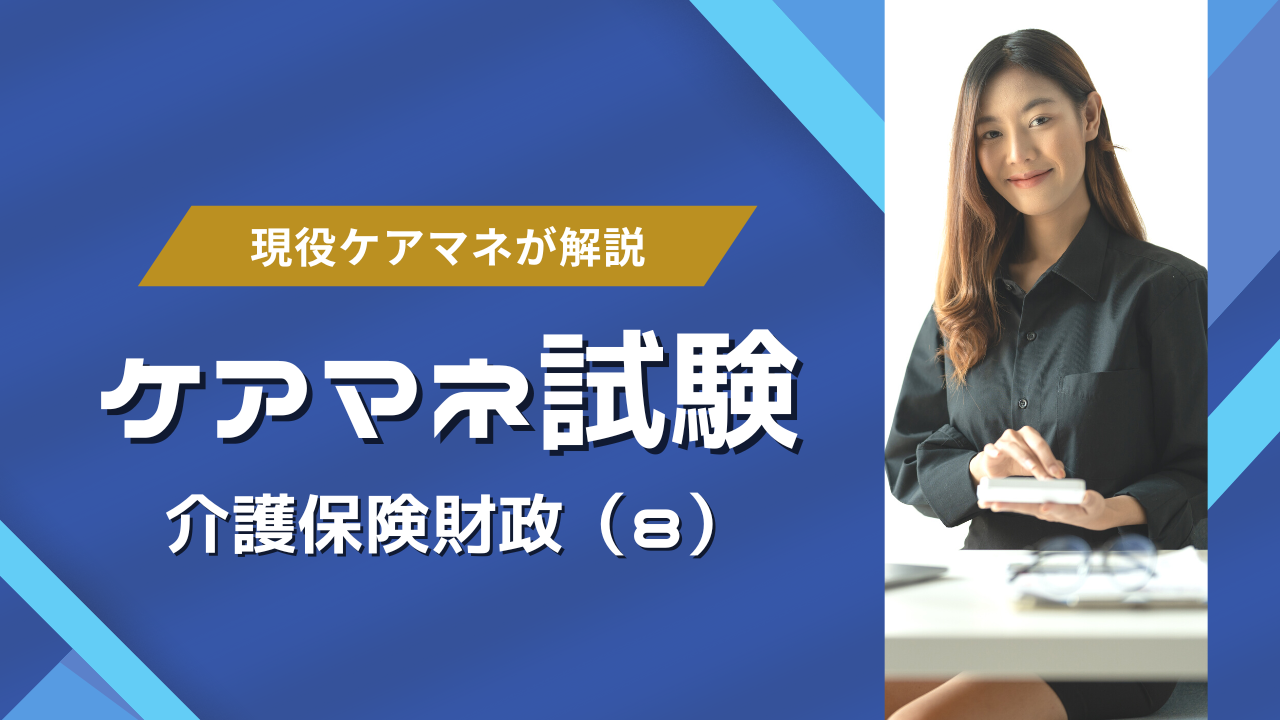

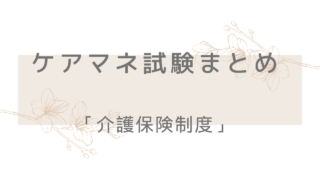
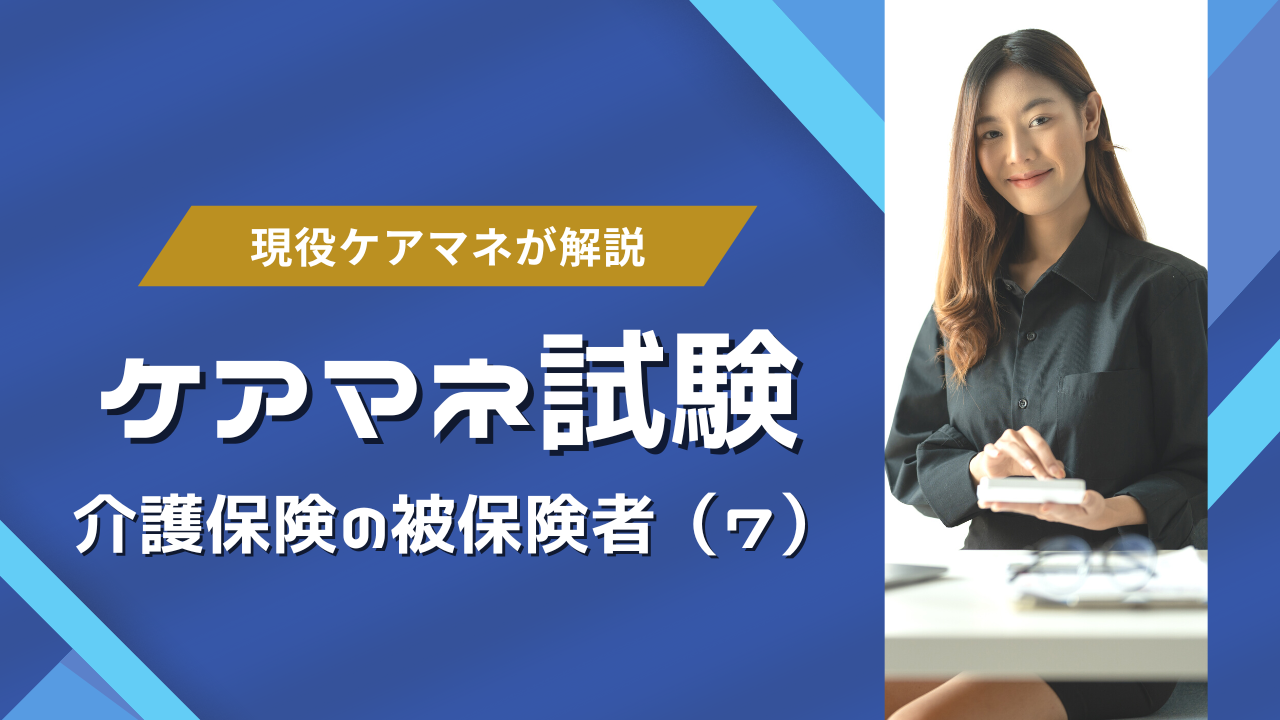
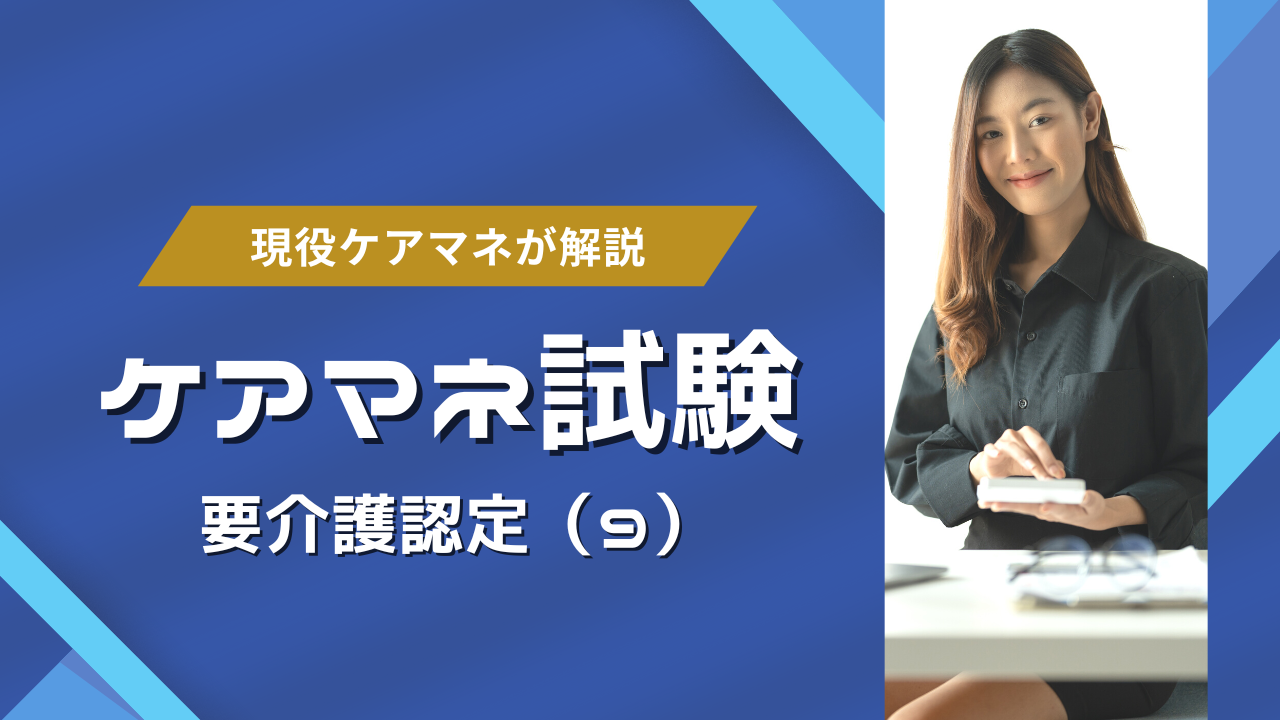
コメント